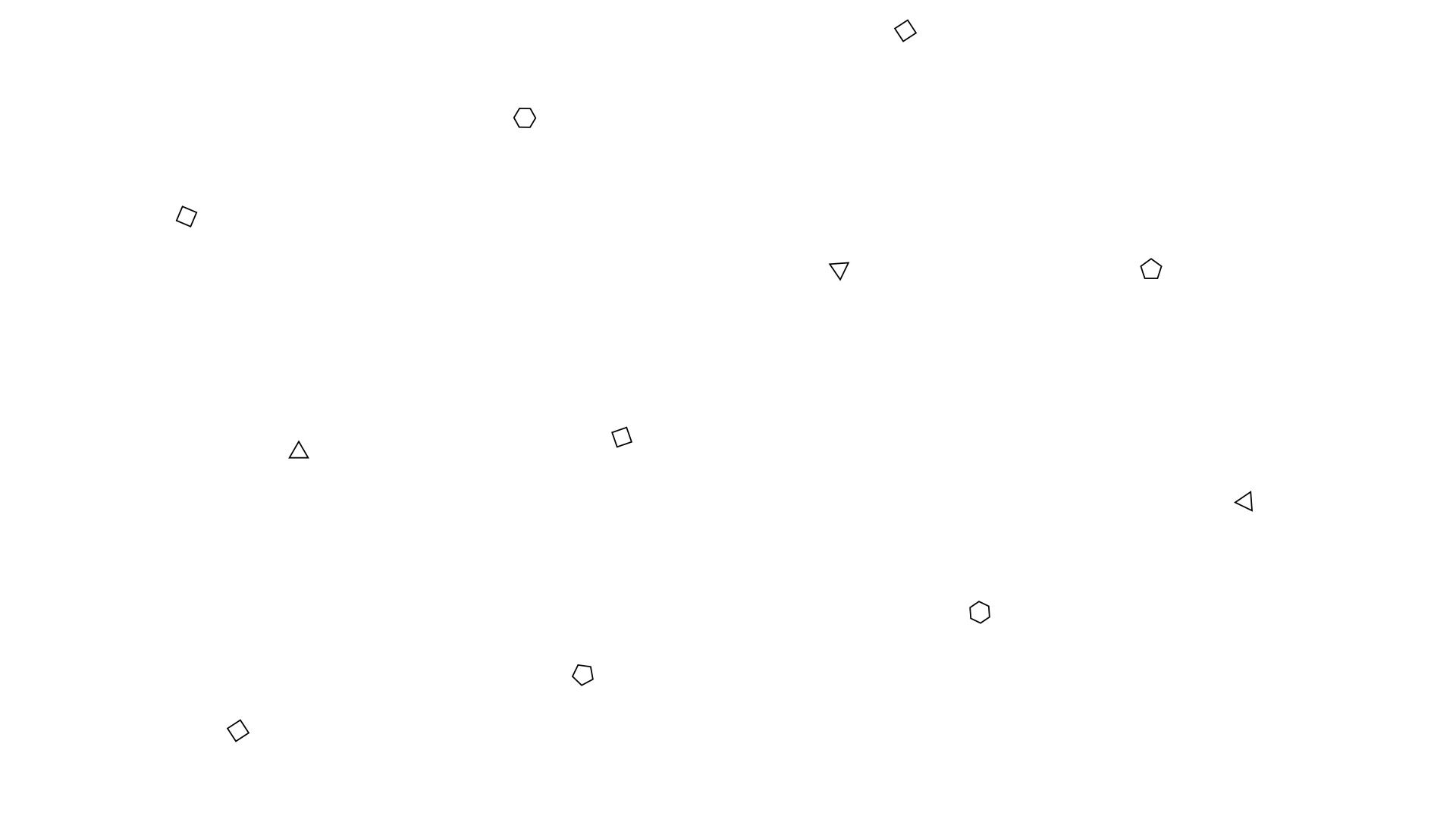
-
8
雨宮と何度目かの食事の時、彼女が時折する淋しい顔が気になった。
彼女と親しくなり左手の薬指のリングの意味も、今の状態も少しずつ彼女が自分自身の事を話してくれるのは嬉しかった。が、必ずと言っていいほど淋しい顔をする事が増えた。雨宮は結婚していたが、彼女の夫とは死別していた。
愛娘はいるが教育費などを稼ぐ為実家に預けているのだと。
娘には本当に申し訳ないわ。と何時も言っていた。
あなたの気持ちはきっと伝わっている。私が保証する。と言っては笑顔を見せていた。何時もはお昼ぐらいに食事をしていた。しかし今日に限っては遅く迄ワイルド君との技術者と話し込んでしまった。
ワイルド君は、
「お前も相変わらずだなぁ。電話じゃダメなのか?」
と言う始末で更には、
「俺定時だから上がるわ。今度飲みに行こうぜ」
と言って帰って行った。
何時もの甘い香りだけ残して。
流石のワイルド君の上司も呆れていたが、私は押しかけてしまった手前、乾いた笑いだけ出てしまった。「もうこんな時間だ。早く帰らねば」
すでに何度も来た事のある勝手知ったるなんとやらだ。
足早に従業員出口に向かう。ふわっと甘い香りがした。
ワイルド君はまだ居るのだろうか?辺りを見渡しても影が無い。
気のせいか…と、暗くなってきた廊下を駆ける。
出口手前で思いがけない人に出会った。
雨宮だ。いや、雨宮と誰か居る。
雨宮の腕を掴んでいる男の姿が映った瞬間、足が其方に向けられた。「やめ…!」
「何嫌がってんだよ?生娘じゃないくせに!」男は雨宮に掌を振り下ろそうとした。
「…!」
身構えるよりも早く、キースが男の振り上げた手を掴んでいた。
「んだ⁈部外者は早く行けよ」
「私は女性に手を上げているところを見て黙っているほどバカじゃ無い」ギリ…と力を入れ、睨みつける。
暗い場所で顔は見えなくても、怒りに震えているオーラが出ている。「彼女を離していただきたい。でないとこのまま力任せに折ってしまいそうだ…」
「ひいい!」乱暴に彼女の手を突き放し、キースが受け止めた。
その隙に男は脱兎の如く逃げる。「あの、ごめんなさい…」
「大丈夫かい?」雨宮は少しだけ震えていた。
細く薄い肩がとても見ていられなかった。「途中迄送って行くよ」
「あ、でも…」
「私はあなたの嫌がる事はしない。神に誓っても。そんなあなたを一人に出来るほど私は冷徹ではないよ。ダメだと言われてもお願いしたい」
「ありがとう。キース」
「どう致しまして」少し歩いたところで雨宮が、お腹が空いた。と言い出した。
彼女なりに気を遣っているのだと。
いたたまれ無い空気を自ら変えようとしている。
強い女性だとますます思った。彼女の会社より少し離れたゴールドステージに近いレストランに立ち寄った。
雨宮がこんな高いところは勿体無いわ。と言い出した時にキースは吹き出した。「ここだとセキュリティーもしっかりしているし、何より私がご馳走したいんだ」
「全くあなたには驚かされてばかりね」ようやく彼女が笑顔を見せ出した。
緊張の糸がやっと切れ出したのだろう。雨宮と自分の顔が緩やかになるのを感じた。少しお酒が入って頃に「どうして何も聞かないの?」とポツリと言い出した。
「其れは聞いていい事なのかい?」
彼女の姿を見て、それを言い出せるはずも無い。
「多分あなたが思っているほど私は綺麗じゃないわ…」
「どうして?こんなに綺麗な瞳なのに…」手を頬に持って行くと彼女はビク…と身構えた。
辛い目にあってたんだね。
そんな事はないわ。と彼女が言う。「安心して欲しい。私は決してあなたを傷つけない」
彼女の頬に触れた。
気丈に振舞っているがあんな事の後だ。其れでも嫌がるそぶりもなくじっと私を見つめる。綺麗な琥珀色だ。
最初から心を掴んでしまったその瞳。
髪に手を添えると艶やかな髪が指に絡む。ん…
雨宮が鼻か抜ける甘い声を出す。
どうしてだろうその行為がとても淫靡で官能的に見えた。「お願い…。私を一人にしないで…。今日だけ…。今日だけでいい…」
肩を震わせ琥珀色の瞳が悲しみに揺らいでいた。
大変不謹慎だが、其れでも彼女が美しいと思ってしまった。