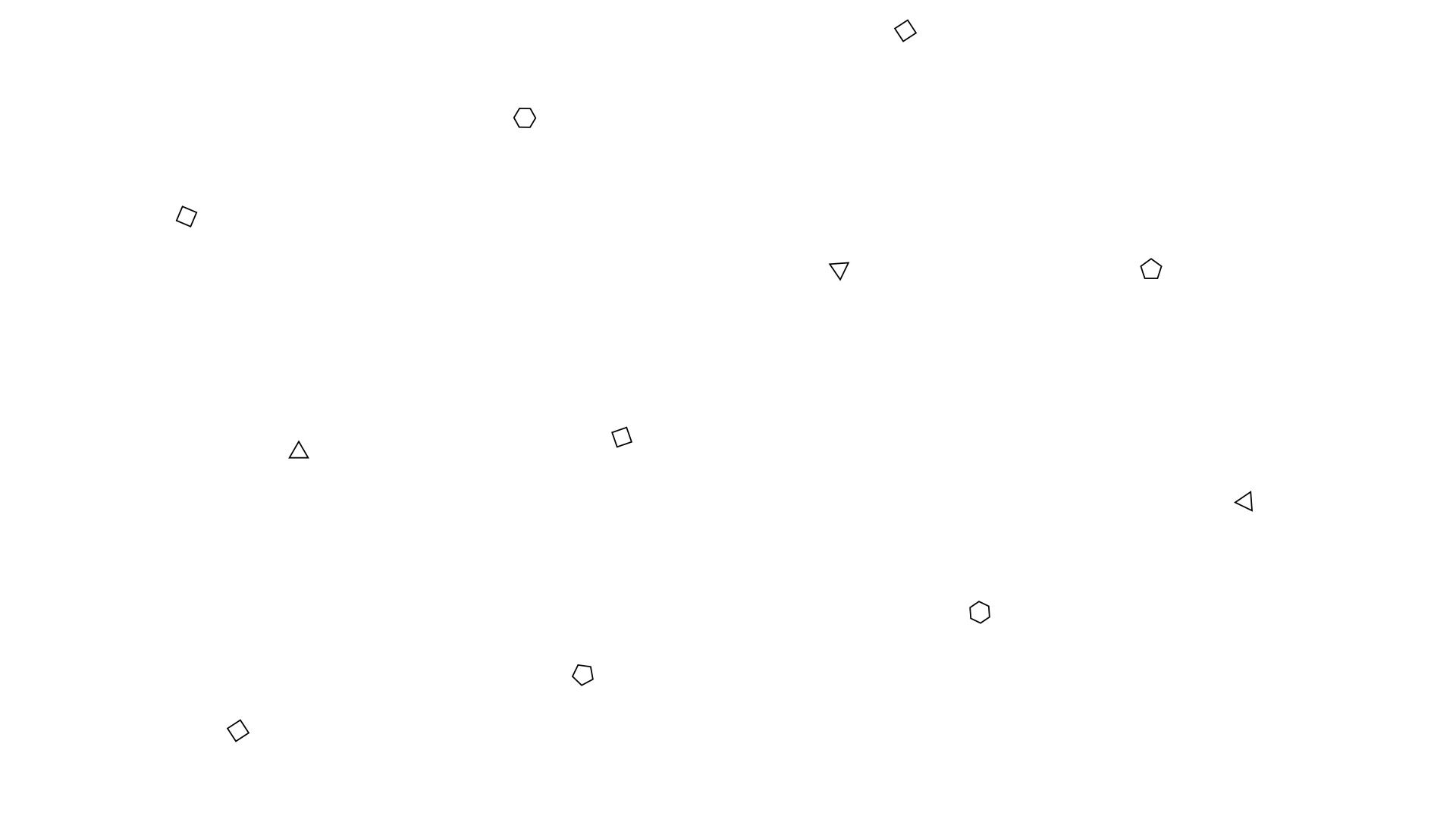
「ようスカイハイ今日も熱心だな?」
「そんな事無いよ。ワイルド君」
「半年だっけ?」
「そんなに経ってしまったのかったのかい?私は気づかなかった。気付けなかった」
「まぁ気落ちすんなよ。いつか会えるって」
「…………」
あの日からパタリと彼女を見なくなった。
雨宮と言う名前しか分からず、所属先、連絡先すらキースは知らなかった。
時にはワイルドタイガーに子どものように問い詰めた事もある。
それが無駄だって事を分かってていても。
そんな私にもワイルド君は優しく髪を撫でる。
こんなにも自分が愚かな子供だったのかと嘆かずにはいられなかった。
ただ目の前は忙しく過ぎる。
ヒーローとしても一社会人としても。
中間成績でキースは1位を独走していた。
2位はワイルドタイガーだ。よく頑張ってるな!と背中をみんなでバンバン叩かれ、顔では笑っているものの本当のところは名前と自分自身がメディアに出るようになれば彼女が気付いてくれるのでは無いか?と言う気持ちが強かった。
時折ワイルド君の所を訪ねては社内を闇雲に歩く事もある。
彼女に会えると期待しながら。
でもワイルド君が何時も目の前に現れては、早く終わらせて飲みに行こうぜ。と言う事ばかりだった。
時折悲しそうな瞳をして私の髪を撫ぜた。
少しばかり甘い香りがした。
ああ…そうだね。と言う顔がまた作り笑いの顔が張り付いた。
そうだねと言うばかりで誰とも飲みに行ける状態ではなかった。
どう言う顔をすれば彼女を苦しめずに済むか?と自問自答を繰り返した。
「ちょっとスカイハイ。あなた無理してない?」
「何をだい?」
トレーニングルームで声を掛けられた。
引き攣った笑顔だったのかも知れない。声が上ずったかも知れない。
誰よりも洞察力のあるファイヤーエンブレムに、だ。
「あなた…誰を探しているの?」
「誰って?」
「私に向かって惚けないで頂戴。あなたここ半年様子が変よ?」
ファイヤーエンブレムから逃げる術をもたない私は、少しだけ話した。
いつものように笑顔を絶やさず。
とある所の女性が気になっている事。
目の前から居なくなってしまって会えなくなってしまった事。
その女性は甘い香りのする女性だと。
一通り言い終わると、自然に涙が零れた。
あれ?何故だい?どうして?
どうして?
そっとファイヤーエンブレムが抱き寄せた。
「スカイハイ。いえ、キース。それはきっとその女性に恋をして愛してしまったのね」
「恋…?愛…?」
そうか、そうだったんだね。だからこんなに胸が苦しいんだ。
あなたが居なくなって、胸にぽっかりと穴が空いてしまって、分からない感情に押しつぶされそうになって…。
ポタポタと年甲斐もなく涙が零れた。
止まれと念じても止まらない涙が、無性にも辛かった。
こんなにも彼女が自分にとって大切な存在だったんだ…。
優しく私を呼ぶ声も、温かく包み込む笑顔も、琥珀色の悲しい瞳も、髪を撫でる心地良い手がこんなにも私を壊して、こんなにも私の心の奥底に染み渡って離れない。
今更気付いても彼女がいない。
彼女が全て私を攫ってしまって、私はただの抜け殻のようになって…。
出会わなければ良かったのかい?
私は…。
此れが嗚咽と言うものだろう。苦しくて辛くて、でも優しい気持ちになって、彼女を思い出すと胸の奥が熱くなる。
「キース…彼女に会いたい?」
思わぬ言葉が飛び出し、私は力一杯ネイサンの肩を掴む。
ギリ…という音がしたかも知れない。
ネイサンは苦痛で顔を歪める事なく、見据えてくる。
その瞳は何か知っている。と言う瞳の色だった。
「ファイヤー…いや、ネイサン何か知ってるのかい⁉」
「正確には知ってるとは言えないわ。あなたには覚悟がある?」
急かす子供のような質問に、覚悟があるか?と低く鋭い声がトレーニングルームに響く。
「どうしてネイサンは含んだ言い方ばかりするんだい。私は彼女に会いたい!彼女を離したく無い」
精一杯、食らい付く。
彼女に会いたい!彼女自身から別れの言葉を聞かないと私の心が帰ってこない。
たとえ叶わぬ恋であったとしても、何もしないで無くなってしまうよりは自分の言葉を気持ちをぶつけたかった。
「分かったわ。ヒントを出すから、後はあなた自身で答えを出しなさい。いいわね?辛い言い方になるけど答えを見極められるいい機会だと思って頂戴」
ネイサンが言ったヒントは『香り』だった。
それ以上は何も言わなかった。いや、言ってはいけない状況だったんだろう…。
彼女はいつも私の知りたい答えを出してくれていた。
トレーニングルームで考えてはいたが、どうも答えが出てこない。
彼女はいつも甘い香りがしていた。
「おーってあれ?スカイハイだけ?」
唐突にワイルド君がトレーニングルームに現れた。
いやここは皆で使用するもので、唐突と言う言い方はおかしかった。
「ああ、ワイルド君。さっき迄ファイヤー君が居たんだ」
「そっかー。アントンが居たら今日飲みに誘うとしたのに…」
甘い香りが鼻を擽る。
記憶の片隅にある甘い香り。
「次期KOH様が何つー顔してんだよー。俺にそんな顔見せるなんて良いのかな~?抜かしちゃうよ~?」
口角が上がり、ニカッと笑う。
思わず一緒につられて笑う。
そうそう。お前はいい男なんだから、笑ってなさい。と髪をクシャクシャと撫ぜる。
少しだけ甘い香りが心地良い。一緒に居ると安心する。
「あ、あのワイルド君。私じゃダメかな?今夜飲みに行く相手は?」
今日は通常業務だけで、取材等ないんだ。と付け足す。
「よし。じゃあ今日は久しぶりに俺ン家に来るか?宅飲みも乙なもんだ」
独特な形の顎鬚に手をあて少し考え、お前は何が好きなんだっけ?と下から覗き込んで来る。
ドキリとした。
琥珀色の瞳が心臓を掴んだかと思った。
久しぶりに間近で見た彼の顔が彼女と被ってしまった。
あまい甘い香りがそう思わせたのだろうか?
ああ…、そうだね。何でも好きだよ。毎回外で飲んでると結構かかるからね。と言うのが精一杯だった。
「お前は俺より稼いでるんだからな~。羨ましいぜ~。キース俺の家知ってるよな?終わったらそのまま来いよ。色々作って待ってやるよ」
了解した。と言うとそそくさとそこから離れた。
胸の高まりと、何故動揺したと疑問符ばかりがめぐる。
彼とはよく顔を合わせている。仕事で。
何かと気を遣ってよく飲みに行って、よく私の話を聞いてくれて…、よく…よく…。
ワイルド君と話す時あの甘い香りが好きだ。
彼女と、同…じ…甘い…香り………?
何故気付かなかった?
どうして⁉いや、でも…。同じ香水何て沢山売られているのかもしれない。
たまたま…偶然…?
ネイサンが言って居た事はこう言う事だった⁉いや、彼女のぬくもりは覚えている。
柔らかな肢体も、乳房も声も。
さっき迄話していたワイルドタイガーは男だ。
細い身体で、でも力強くて…。腕なんて細過ぎて折れてしまいそうで…。
声が大体違うじゃないか…。
動揺を隠しきれない。
確かめるしか無い。
もし彼女でなければ、笑って誤魔化そう。
もし彼女だったら、私は理性を保てるのだろうか?
******
ブロンドステージも中でも、比較的大きな住宅街に虎徹の自宅はある。
モノレールで途中迄向かい、少しだけ酒の肴を買う。
彼は少し塩っ辛いものが好きで、淡白な魚が好きで、でも小食で、少しだけ食べてお酒の味を楽しむ飲み方をする。
「よう!早かったな!狭い我が家だがようこそ」
「ああ、すまない。今日はただお邪魔するのも忍びないので、色々買ってきたよ」
「おおー此れは越乃寒梅!なかなか手に入らないんだぞー!よく手に入ったな!」
「スポンサーの方に相談したら、日本酒好きなら是非此れを。と渡されてね。私は日本酒を飲んだ事がなくて、是非虎徹君と呑んでみたくて」
「ありがとう!そしてありがとう!キースの真似だ!」
極上のお酒が目の前だと、ワイルド君は上機嫌になる。
1年以上仕事帰りに呑んで来た仲だからよくわかる。
ウキウキした声で私を迎え入れてくれた。
出された料理はどれも素晴らしく、本当にワイルド君一人が作ったか疑う程だ。
彼曰く男は料理の一つも出来ないともてないぞ。
「美味しい…何故こんなにも甘いんだい?」
「おーよく分かったなぁ。越乃寒梅は日本酒の中でも雑味が少なく、辛味がない。日本酒初心者なら甘く飲みやすいんだ」
ご機嫌な彼はいつもより早いペースで喉に通す。
終始ご機嫌で、そんなに喜んでくれて持って来て正解だったよ。と言うと、こっちが招いたのに申し訳ないなぁ。と笑顔が零れた。
向かい合わせに座っていたテーブルの上を手がのびた。
「キース…?」
届いた手で頬に触れた。
きめ細かい肌で手に吸い付いて来る。
「ちょ、キースどうした?」
「…」
手を一向に止めなかった。
もっと確かめたかった。東洋人だからみんなこんなに肌が綺麗なんだと。漆黒の髪で、琥珀色の瞳なんだと。
そこに甘い香りがするのは至極当然なんだと…。
でもそう思えば思う程彼女が脳裏から離れない。離したくない気持ちが溢れる。
少しだけ立ち上がり唇に触れる。
「ー!!」
藻掻いている手も身体も、関係ない。
確かめたい。
唇を離すと、ハァハァと息を荒げ睨みつける。
「俺はこんな趣味はないぞ!」
「甘い…」
顎に手をかけた時少しだけ不自然な粘着力を感じた。
顎鬚に親指を当てると少しだけ捲れるような感覚があった。
甘さを確かめたくて首筋を甘噛みする。
「や、め!」
声が出たと同時に顎鬚が捲れた。
付け髭?もう片方を急いで捲る。
付け髭の裏には何やらチップのようなものが付いていた。
「キース!」
「⁉」
いつものワイルド君の声では無い。私が聞きたかった声がそこにあった。
「虎徹…いや、雨宮?」
「違!」
逃げられまいと片手を掴み、声の主を無理に引っ張った。
苦痛の声を出したが、今は気遣える程余裕が無い。
空いた片方の手で腰に手を回す。
会いたかった!声を聞きたかった!
貪るような口づけを幾度も行う。
その度に逃れようと暴れる。
「逃げない。だから離してくれ」
聞きたかった声の主が低い声を出す。
あ、すまない。興奮してしまって…。と腰に回していた手を離した。
もう片手も。と言われたが、此れだけは離したく無いと拒絶した。
「キースを…騙すつもりじゃなかった。それは信じてくれ」
重く言葉を選びながら話す。
「私は君をずっと探していた。虎徹君は知っていたよね?どうして言ってくれなかったんだい?ずっとずっと寂しかった。辛かった」
腰に顔を埋めながら彼女の言葉を聞き出す前に泣き崩れてしまった。
「俺はヒーローで鏑木虎徹と言うのも本名だ。雨宮ってのはな、旦那の苗字だよ」
優しく髪を撫でる。
いつもの虎徹君が、雨宮と言う彼女が私にしてくれていたように。
「俺 がヒーローとしてデビューする時に自分のエゴで、ヒーローとしている時は男として振舞いたいってな。今は色んなスポンサーが付いてヒーロー業界も潤って来 てるが何分景気が悪いとな色々したくない仕事が出て来てしまう。俺はそれをしたく無かったんだ。女と言うだけでそんな事の為にヒーローになったんじゃ無 い」
ぎゅう…と腰に回す手に力が入る。
「だけど会社でもヒーローって言うのは秘密裏にしたいもんさ。だから会社にいる時は素の自分で仕事をこなしてたんだぜ」
「素の虎徹君が素敵だ」
「そんな男前のセリフは、俺の顔を見て言ってくれよ。あの時キースを見かけた時、絶対俺だと気付かないだろうと思っていた」
「気付かないさ…。とても綺麗で見惚れてしまったんだ…」
ふふふ…。と優しい声が頭から降って来る。
撫でる手も温かい。
「何度か食事をして、アレだ…俺もキースに惹かれてたんだろうな。でも俺は綺麗じゃない。その…嫌な仕事も…した事がある」
ふるふると震える声と、流れている涙が愛しくて、思わず舌で舐めとる。
虎徹君は目を見開いて、どうもキースにはかなわない。と笑ってみせる。
「虎徹君は汚く無い。こんなに涙が甘いんだ。こんなに私の胸が高鳴る」
虎徹の手を自分の胸に当てる。
心臓の音が伝わるだろうか?この気持ちが伝わるだろうか?
「嫌な仕事…を聞いてもか⁉それでもその澄んだ瞳で言えるのか?」
「私は最初に誓ったはずだ。君を傷つける事をしない。と」
「俺はお前が会った…あの男の…慰み者だった…んだよ。個人的な仕事として…。酷く犯されたよ。言うのも悍ましいぐらいに…」
ガタガタ震える。あの時のように酷く怯えている。
辛かったんだね。もう大丈夫。私がいる。
「虎徹君は綺麗だ!綺麗なんだ!お願いだ!どうか自分を卑下するのはやめてくれないだろうか?私は過去の虎徹君も、今の虎徹君も愛してるんだ。あなたを苦しめる奴が現れたら、私があなたを守る。私では役不足だろうか?」
「キース…意味分かって言ってんのか…?」
かああと顔を真っ赤にして見つめて来る。
本当に、本当に、あなたは私の心を満たす。
「意味?愛している。大好きだ。何度でも言うよ。大好きだそして愛している」
「ば、恥ずかしい事を真顔で言うな…!俺はバツイチのコブ付きなんだ。そんな俺を…」
「是非あなたが大事にしている全てを、私に預けてくれてもいいだろうか?虎徹…。あなたが本当に好きな相手が亡くなった旦那様でも構わない。私はあなたを本気で愛している。この気持ちに嘘偽りは無いよ」
「いいのか?俺はお前が夢見ていた雨宮とはかけ離れてガサツだし」
「虎徹…あなたはキュートだ」
「よく飲んだくれてるし…」
「私が毎日付き合うよ」
「年上だし…」
「虎徹は素敵だよ」
「男の格好してるから、胸はサラシで押し潰されて形は良く無いし…」
「全てが綺麗だよ」
「キース…いいのか?」
「虎徹はありのままの虎徹でいて欲しい。ヒーローの虎徹にも私は惹かれていたから気にしないで欲しい」
薄く紅も引かれていない唇に、子どものような口づけをする。
琥珀色の瞳が優しく催促し、それに答える。
あなたは汚れてはいない。
私だけの愛しいヒーロー。
If I had to choose between breathing and loving you I would use my last breath to tell you I love you.
「もし、呼吸をするか君を愛するかを選ばなければいけないとしたら、僕は最後の息を君に「愛してるよ。」と言うために使おう。」
******
おまけ
「スカイハイさん!この素敵な女性は誰ですか⁉」
「え?」
ヒーローイベントの時女性たちの囲まれた時に出て来た言葉だ。
彼女達はゴシック紙の一部な記事を突きつけて来る。
スカイハイのヒーロースーツ姿に寄り添うスレンダーな女性が写っていた。
マスク下で、ふふふと笑みを零しながら
「彼女は最高のヒーローさ!」
と一言だけしか話さなかった。
******
「ネイサン…お前だろう。キースに俺の使ってる香水がどうのこうのって言ったんだろ⁈」
「あら?私は、品のある甘い香りね。と、犬のように嗅いでらっしゃい。ぐらいしか言ってないわよ?」
「うーあいつやっぱり犬だな…」
「その犬にほだされたのは何処のどなたかしら?」
「~~‼うっせえ!ネイサンこそアントンとどうなんだよ⁉」
「ふふ…。秘密よ♡」
「きたねぇ。でも羨ましいぐらいいい女。アントンも早くくっつけばいいのに…」
「そうね。あなた達の熱に早く当てられてしまえば良いのよ」
******
雨宮。お前が大事にしていたあいつがやっと前を向いて歩きだした。
キースは良い奴だ。好青年を絵に描いたような奴で、お前と若干雰囲気が被るんだぜ?あいつが惹かれるのも無理は無い。
きっと楓ちゃんも懐くだろう。心配すんな。
あの二人なら雨宮が出る幕がねぇよ…
カランとグラスの氷が溶けて落ちる。
アントニオの前にはグラスが二つ並んでいた。